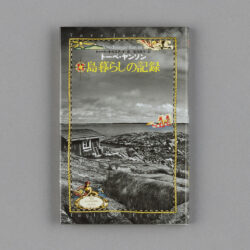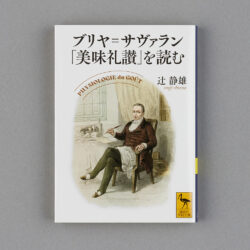そこに誰がいて、どんな言葉をかわしたのか
古い小説やエッセイを読んでいると、文中で実在の喫茶店に出くわすことがある。それが数回重なると不思議な親しみが湧き始め、訪れたこともないのにその内装や雰囲気を思い浮かべることができるようになってくる。かつて新宿で営業した高名な「風月堂」の場合、たしか最初に目にしたのが、永島慎二の漫画『フーテン』だったから尚更だろう。永島タッチの若者たちが訪れる、そこへ行けば必ず知った顔がいて、待ち合わせや、話し合いに使われ、常に賑わいを見せる喫茶店として視覚的にも刷り込まれている。
先日、主催するブックトークの準備もあって、随分久しぶりに庄司薫の「薫くん四部作」を読み返してみると、作中で忘れかけていた「風月堂」に出くわした。シリーズ最終作に位置づけられる『ぼくの大好きな青髭』は、薫くんが新宿の街を徘徊し、退廃的な若者たちと一時的に交流し、思索を巡らせるという内容で、学生運動の挫折と大量消費社会の訪れとともに若い世代を侵しつつあったニヒリズムをひとつのテーマにしている。自殺を図った友人の足跡を辿る中で薫くんは「風月堂」に立ち寄り、その様子はこのように描写される。
「風月堂の大きなガラスの扉の中に入ると、極端に冷房のきいた空気とヴィヴァルディの音楽が、ぼくのからだからふき出していた汗を一気に冷やしてくれた。(中略)前に来たときもそうだったけど、前衛芸術家風(?)とでもいうのかヒッピー風とでもいうのか、それぞれ気ままな現代的風俗で身ごしらえした若者たちが店いっぱいに溢れていた」
二階席まである広い店内を埋め尽くす、芸術家気取りの客たちを眺めながら、そのステレオタイプぶりを揶揄した友人の言葉を薫くんは思い出す。皆が前衛芸術家を気取りはじめ、本物の芸術家とフォロワーの見分けさえつかなくなってしまうと、芸術家を気取る目立ちたがり屋の若者さえも、特別な視線を浴びる特権を損なってしまうだろう。つまり、流行り廃りに本質が覆われてしまう情報消費社会の訪れを薫くんたちは予見、危惧し、店内のヒッピーや芸術家かぶれたちを、風前の灯火として切なく眺めているのだ。しかし、彼らに対する批判に終始せず、登場人物の女性には「風月堂」に集まる彼らの若さゆえの輝きと、時代とともに生きる刹那的熱気を肯定させてもいるのが、著者のまなざしのやさしさだ。ここで描かれる1969年の夏からたった4年後に風月堂はその歴史に幕を閉じる。
しかしこのようにして、フィクションや回想記の中で描かれた喫茶店は幸福だ。賑わっては消えていく飲食店の殆どは記録に遺されることがない。例えば、建築物として特筆すべきものがある店は少なくない。しかし、古い建築雑誌や、商店建築の本に遺されたそれらの写真は、無人、あるいは動きのない静止した空間である。そこにどのような客が訪れ、彼らはどのような会話をし、どのようにその店を使ったのかを、うかがい知ることはできない。
喫茶店はコーヒーやケーキを提供する箱ではない。とくに一時代の文化を支えた店というものは、このような客の雰囲気と会話が記録されることなしに、その存在が語り継がれることはないだろう。言葉でスケッチされる喫茶店は幸福だ。