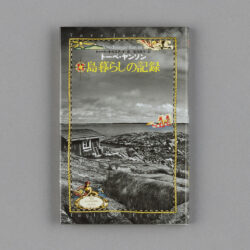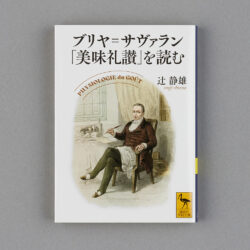憩いへの貪欲さ
建築家の自邸にはそのエッセンスが詰まっているという。生涯を独身で貫いたフィリップ・ジョンソンは、全面ガラス張りの自邸を建て、潔癖症の彼はスイッチ類を一切露出させず、衣食住以外の機能をすべて別棟にまとめてしまったという。また、吉阪隆正は自邸に、師コルビュジエのトレードマークでもあったピロティを設け、門も塀もない庭を開放し、創作と交流の場とした。施主も設計も自身であるが故に思う存分実験ができ、理想を追求することが出来るのだろう。
戦後わが国では、復員兵の帰還とベビーブームによる住宅難に備え、臨時建築制限令が公布され、しばらくの間、新築住宅の上限面積は12坪に制限されていた。終戦直後のアメリカのような都市近郊の住宅群「サバービア」が誕生するのはもう少し後の話。そんな最中に自邸を設計、新築したのが吉田謙吉だった。
吉田はいわゆる建築家ではないが、舞台装置家として活躍するのみならず、その延長としてバーなどの店舗設計もいくつか手掛けている。今和次郎に師事し、共著『モデルノロジオ』を刊行、考現学の中心人物であり、バラック装飾社として関東大震災後の焼け野原に立つバラックを装飾することで復興を推し進めるような活動にも従事した。
そんな彼がたった12坪に詰め込んだアイデアは驚くべきものだった。まず、演劇人である彼は、一階の大部分を「ホール兼居間」と「ステージ兼アトリエ」に割いた。その二部屋は赤い緞帳で仕切られ、「ステージ兼アトリエ」の方ではときに舞台装置を制作するスペースとなり、撮影スタジオとして使われることも、落語会のような催事が開かれ実際にステージとして使われることもあったという。舞台でいう客席にあたる「ホール兼居間」の方では寝室、台所以外の用途はほぼ行われる多目的スペースとして機能した。
その「ホール兼居間」の端には半円形のテーブルが壁に設置されており、その周りに置いたハイスツールとともに「スタンド」スペースとして機能し、即席の家庭内喫茶店として使われたという。
それを受けて「狭いながらも楽しい我が家」だとか「暮らしを豊かにする工夫」などという、ありきたりの感想を述べたいわけではない。狭小住宅の貴重なスペースを割いてまでも、喫茶気分でコーヒーを嗜まんとした吉田謙吉の憩いに対する貪欲さにはどこか胸を打たれるものがある。ル・コルビュジエは住宅は機械であると定義したが、バラック装飾社の活動において謙吉と今和次郎は住まいや店舗は雨風を凌ぐためだけのものではないと看破した。最も悲惨な震災の直後、荒れ地から立ち上がらんとした人々の生命力に、彼らは色彩と遊びを加えた。機能ではなくゆとりや彩りに目を向けてこそデザインではないかと。
空き地や公園のような都市の隙間が急速に失われ、住宅内が既製品で埋め尽くされる昨今、12坪の家の「スタンド」は、窮屈な現代への反抗と脱走へのヒントを与えてくれているように思えてならない。