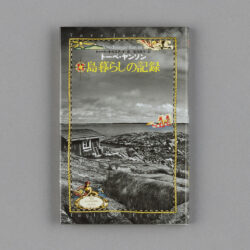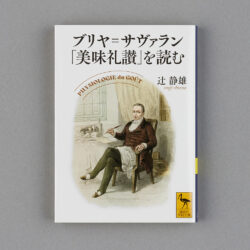エコール・ド・ギンザ
「植草甚一さんが若いころ、ぼくの親父やその仲間のあとをよくついて歩いたものだ、と話してくれたことがある。劇場の帰りに親父たちは築地から銀座に出て、喫茶店で芝居談義などをしており、植草さんは少し離れたテーブルで、その話をじっと聞いていたというのだ」
なんと美しい光景だろう。個人的に幾度も読み返した座右の書の一つである和田誠の著作『銀座界隈ドキドキの日々』からの一節である。築地小劇場の創立メンバーの一人であり、ラジオ演出の仕事に携わった和田の父はコーヒー好きで、馴染みの喫茶店をいくつも持っていたようだ。タウン誌「銀座百点」に連載されたこの回想記は、銀座という町そのものが主人公の物語としても読むことができる。本書自体は銀座のデザイン会社、ライトパブリシティへ入社の挨拶に足を運ぶシーンで始まるが、和田誠と銀座の物語は時系列で言えば、上に引用した父の回想からスタートする。
ライトパブリシティに入社後、昼休みにはライバル会社でもある日本デザインセンターに務める横尾忠則や宇野亜喜良たちと喫茶店やバーで語り合い、寺山修司ら作家たちや、八木正生らミュージシャンたちとも、銀座の街そのものをオフィス代わりに打ち合わせし、仕事を重ねている。若い頃からジャズ批評を愛読していたという植草甚一とは草月アートセンターの仕事で出会い、イラストレーターであることを告げると、その後会うたびに外国雑誌の面白いイラストレーションの切り抜きをくれたという。まさに街が学校であり、教え子が教師となり、次の世代に知識を授ける循環がごく自然に描かれている。ここで回想される銀座は、華やかな都市ではなく、ある種のスモールコミュニティであり学び場なのだ。
本書の後半では街と仕事の変貌が綴られる。1967年末、銀座の路上を走る都電が廃止され、和田はキャノンの新聞広告で消えゆく都電の姿を惜しんだ。「クルマという新興勢力が風情のあるものを駆逐していく」ことを嘆いたその頃、高度経済成長期はピークを迎え、広告の仕事も倍増する。それと同時に広告代理店が幅を利かせはじめ、専門家である多くのデザイナーたちはその下請けのような仕事を受けざるをえなくなる。路電と徒歩から車へ、職人仕事から分業へ。高度資本主義社会への分水嶺を、銀座という街がいち早く示していたかのようだ。
本書の最後で、そのような状況に背を向けるかのように、和田はライトパブリシティを退社し、フリーランスのデザイナーとして自宅兼仕事場を青山へと移す。その後も和田は、月刊誌「話の特集」のアートディレクターを編集にも口をだすことを条件に無償で引き受けたり、書籍の裏表紙に掲載するバーコードを美的理由から拒み続けたりと、仕事全体をトータルに管理する職人であることにこだわり続けた。
銀座が街の王様で、喫茶店がその中心だった刺激的な時代がかつてあった。いま、街の王様があるとすればそれはどこで、その中心には何があるのだろう。