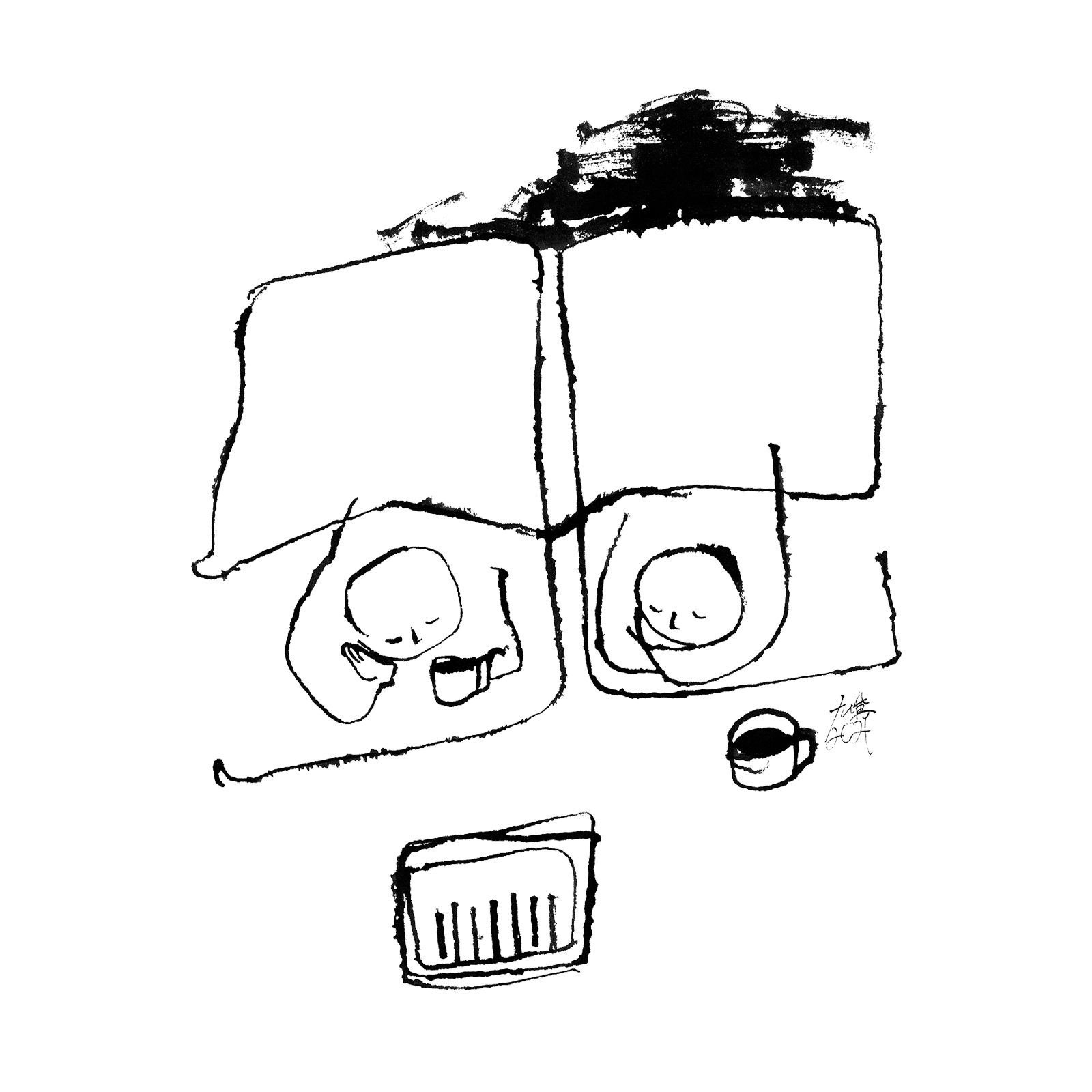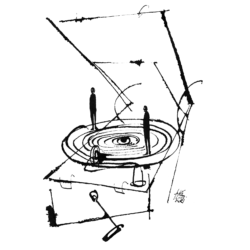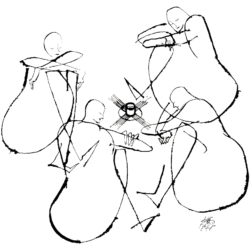「喫茶店について」
私がコーヒーを飲み始めたのは・・・たぶん小学1年生くらいのことだったと思う。土曜日の夜は普段早く寝かされていた子供たちにとって遅くまでテレビを見ることを許された特別な時間だった。『全員集合!』を見てから『土曜ワイド劇場』が始まるまでの間にインスタントコーヒーを準備する。その時に食べるブルボンのお菓子が特別な夜をさらに豊かにした。夜の居間でテレビを囲みながら敷き詰めた布団の隙間で食べるお菓子とコーヒー。インスタントコーヒーでも十分に美味しくて、コーヒーフレッシュの容器に残ったミルクを舐める背徳感もたまらなかった。その頃からコーヒーに砂糖は入れない。親戚の家に泊まりに行った時「この子達、コーヒー飲むらしいわ。砂糖もなしで」と言われて驚かれたことが不思議だった。私たちは夜にコーヒーを飲んでいてそれによって眠れなかったことなど一度もなかったからコーヒーの何がだめなのかわからなかったのだ。
高校生になってアルバイトで得た小遣いで学校帰りに買い食いをするようになる。その頃はカフェブームの始まりで20〜30代くらいの若い人が始めた個性的なカフェに通った。カフェの店主は学校では出会うことのない音楽や映画や文学の先生だった。20歳の時に古い蔵を改装したカフェで展覧会をした。展示した作品が売れた時の喜びは忘れられない。自分がとてつもなく大きな一歩を踏み出したような誇らしい気持ちになったのだった。その辺りからカフェブームは活況を呈して、雑誌を手にカフェを巡る人が増え、人気店は外に人が並ぶようになった。店主も忙しすぎて、何時間もだらだらと最近見た映画や展覧会の話をし続けるなんていうことが難しくなった。カフェから喫茶店への波が訪れて、今度は街の小さな古い喫茶店に若い人が押し寄せた。私が好きだったたまに行く小さな喫茶店は女三世代(お婆さん、奥さん、孫)が働いていて、いつもテレビがついていて、近所のおじいさんが新聞を読んだり、たわいもない会話をしていて、そういうのが本当に心地よかった。カフェオレを頼むと煮詰まったコーヒーに牛乳をドバッと注がれるのでたまにとてもぬるくて、そこのコーヒーはしみじみと「おいしくないなぁ」と思うのだけれどそれで良かった。雑誌のカフェ特集で紹介されていたりするとこそばゆいような気持ちになる。昔そのあたりにたくさんあった似たような店が、それぞれの個人的な理由により無くなっていったあとに、ただ残っているだけで「レトロ」で「老舗」と呼ばれて重宝されているのだけど、ただそのまま同じことの繰り返しをしてきた人たちのその日常は大したものなのだ。「護ってきた」というほどの気合もない感じが私は好きで誰に気にされなくても季節の営みと同じ、春には必ず咲いてみる道端の花のように愛おしい。
東京に頻繁に行くようになってから驚いたのはあまりにも喫茶店がないことだった。少し考えたらそれはそうなのだけれど。家賃を考えると一杯数百円のコーヒーで何時間も粘られてはたまったもんではない。フランチャイズのコーヒーショップはコンビニ並みに見つけることができる。ずば抜けておしゃれで美味しいコーヒーを入れるとか、フードメニューに拘っているカフェは行列で、並ぶのも並ばれるのも苦手な私はなかなかそういうところへ出かけない。
今、私がよく通う喫茶店は家族経営で大奥さんも若奥さんも清潔に髪を束ね、キリッと化粧している。コーヒーを自家焙煎する強い香りがして、それと交わるから煙草の匂いがするのもそんなに嫌いではなかったが、最近禁煙になった。若奥さんが私と同い年だということを一昨年の夏知った。