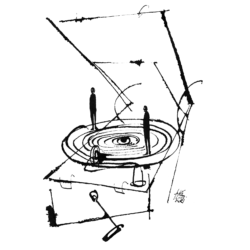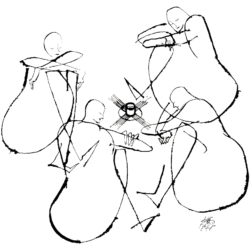授乳する若い母、缶の錆び、そしてコーヒー
中学生の夏休み、家でインスタントコーヒーの粉と砂糖を少しのお湯に溶かして氷を入れて牛乳をドバッと注いで作るコーヒー牛乳とか、高校時代にバイトをしていた阪神競馬場の近くのお好み焼き屋と喫茶店を足して二で割ったような不思議な店で自分が淹れるサイフォンコーヒーとか、21歳の時に初めてヨーロッパを旅してパリからマドリードまで夜行列車に乗って、夜が明けて国境のスペイン側にあるイルンという駅のカフェで飲んだカフェ・コン・レーチェとか、東京の豊島区南長崎の交差点近くのおんぼろアパートから渋谷区恵比寿にある撮影スタジオへ出勤途中に目白通りを歩きながら飲む缶コーヒーとか、思い出すコーヒーはいろいろある。
そんな記憶の中にある実際のコーヒー体験とはちょっと違った、フィクションに登場するファンタジーとしてのコーヒーというのもあったりして、その中でも自分にとって最も強烈な二つがガルシア=マルケスの「大佐に手紙は来ない」とスタインベックの「朝めし」という小説に登場するコーヒーだ。
「大佐に手紙は来ない」の冒頭はこうである。
“コーヒーの缶の蓋を開け、残りを確かめると、わずか小さじ一杯分しかなかった。大佐はかまどから鍋を下ろし、水を半分ほど土間に捨てて、鍋の上で、缶にこびりついたコーヒーの粉をナイフで錆びごと残らずこそげ落とした”
この後、主人公の大佐は寝室で病にふせっている妻にコーヒーを持っていくのだが 「で、あなたのは?」と訊かれて「もう飲んだよ」と大佐は嘘をつく。「まだ大さじ一杯分残っていたんだ」と。かつて内戦に参加していた大佐は、毎週金曜日になると退役軍人への恩給支払いの手紙が届いていると信じて郵便局に確かめに行くのだが一向に手紙は届かないという状況で、朝に飲むコーヒー豆もついに無くなってしまうエピソードから始まる陰鬱な話である。しかし、これを読んだボクは、この缶の錆びの風味たっぷりの煮出したコーヒーを飲んでみたいと思ってしまう。貧しく、慎ましく暮らしている二人がものを分かち合って暮らしているという美談ではなく、得体の知れない強迫観念に取り憑かれたような、どうしようも無い切迫感に満ちた小説なんだけれども。
「朝めし」はアメリカ中西部を移動しながら暮らす綿摘みの季節労働者の一家のテントのそばを、一人の旅人が通りかかり簡素な朝食を共にする、というただそれだけの話。
“あれは夜が明けてまもなくだった。東の山々は濃い藍色だったが、その背後から刺してくる光が、洗ったような赤で山のふちをかすかにいろどっていた。そして、さらにさきへ行くにつれて、私の頭上あたりでは、その光が冷たい灰黒色になり、西のはずれ近くでは、完全に夜のなかに溶け込んでいた”
“若い女はベーコンの皿や、褐色の分厚いパンや、肉汁を入れた鉢や、コーヒー・ポットをならべ、それから自分も箱のそばにすわりこんだ。赤ん坊はまだ寒さから母親の胴着のなかに頭をうずめて乳を吸っていた。そのチュウチュウ吸う音を、私は聞くことができた”
“みんなすばやくがつがつ食い、お代わりをして、またがつがつ食った。そのうちに、腹がいっぱいになり、体が暖かくなった。熱い苦いコーヒーが咽喉を刺激した。私たちはコーヒーかすのたまったわずかばかりの飲み残しを地面に投げすてて、またカップにコーヒーをついだ”
”いまは日の光が色づいてきて、その赤い輝きのために空気がいっそう冷たくなったように思えた。二人の男は東を向いていたので、顔が夜明けの光に輝いていた。私は、ちょっと目を上げたとき、老人の目のなかに、山と、その向こうから射してくる光のイメージが映っているのを見た”
アメリカの大地と光と人間の佇まいが鮮やかな筆致で描かれているこの小説、たった5ページの掌編である。この話を読む度にベーコンとパンとコーヒーの朝食を食べたくなり、また美味しい朝食を食べる度にこの小説のことを思い出す。
そして、いつのまにか自分の記憶の中で、十代の終わりに読んだ二つの小説に登場するコーヒーは渾然一体となって、人生の象徴のような、何かの理想形になっている。旅路と家郷、授乳する若い母、缶の錆び、老いた妻、夜明けの空、そしてコーヒー。
※「大佐に手紙は来ない」の引用は『ガルシア=マルケス中短編傑作集』(野谷文昭=編訳・河出文庫)より
※「朝めし」の引用は『スタインベック短編集』(大久保康雄訳・新潮文庫)より