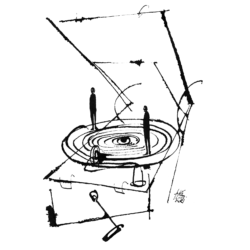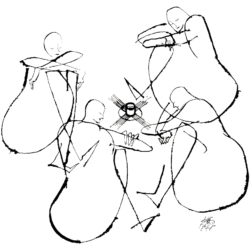ひよっこですが
ひよっこ扱いされなくなってずいぶん経つ。半世紀も生きてきたのだからまあ、あたりまえだ。でも偉くなるには早い。まだまだ伸びしろばかりなのだ。
そんなわたしがひよっこ気分を存分に味わえる店がある。岡山市の自宅から自転車で10分、ドイツ語で「ありがとう」を意味する名を持つ喫茶店。50年の長きにわたって街に鎮座している。
使い込まれた木のドアを開けると深みどりのレザーのシートが目を引く。カウンターとテーブルは暗い色のウッド。シックな店内は常連客でいつもほどよく混んでいる。いらっしゃい。今日もママが明るい調子で迎えてくれた。誰もが歓迎されているという気持ちになれる声に接客業の年季がにじむ。こんにちは。はい、いらっしゃい。窓際の隅の席に座る。
以前、コーヒーを飲みながらこの店の一角をそっと撮った。その写真を次に出す本に掲載させてもらいたくて今日は来たのだ。デザイナーがレイアウトしたPDFを出力したものをママに見せる。「で、本はどこ?この紙は何なん?」あ、これはまだ本ではなくて、仮に配置したものなんです。まず許可をいただこうと思って。「おたく、プロなん?」はいそうです。「わたしはようわからんけど、Kさんはアーティストじゃけぇ、見てもらうわ」
カウンターに紳士が座っていた。ボーダーのシャツにベレー帽。ピカソはボーダーが似合うがこの方も相当似合う。「ここの内装してくれたひとなんよ」店内のカラーリング、すごく品があってすきです。そう伝えるわたしにママは店の奥の絵を指差す。「このひとは絵も描くんよ」
壁には画面いっぱいに描かれたパワフルな金魚。背景は金色に光り、どくどくとエネルギーが立ち上るようだ。作者の紳士は静かにコーヒーを飲みながらつぶやくように言う。奥にあるF1の絵も僕の作品なんですよ。立ち上がって拝見すると、疾走感溢れる前衛的な車の絵があった。もの静かな芸術家の中にたぎる情熱を垣間見る。大げさに褒めることを控え、わたしも座ってコーヒーを飲む。彼のおだやかな時間を揺らしたくない。
本のレイアウトをゆっくり眺め、彼は低い声で言う。いいね。「じゃろ。わたしもええと思うわ」ママは相手が誰であってもマイペースに明るい。これまでとくに名乗らずそっと座るだけだった店で名刺を出す。字がちいそうて読めんわ。ママは笑って花柄のメモ用紙とボールペンをわたしに差し出した。「お名前とお電話番号、ここに書いてちょうだい」
LINEでもメールでもなく、電話番号。古き良き時代の通信方法だ。字を書くのがひさしぶりで筆跡が乱れる。ママはわたしの乱筆のメモをカウンターの中の壁に大事そうに貼ってくれた。で、掲載はしちゃってだいじょうぶですか?「はいはい、ええよ」念のため、本の内容について再度説明したけどママはおそらく半分聞いてない。ええのええの、あなたがすきにしたらええんよ。やりとりを横目に芸術家のボーダー紳士が出ていく。わたしはあたまを下げる。彼は洒落た仕草で片手をあげた。
入れ替わりでドアが開き、女性が3名現れた。この方、写真撮ってるんよ。ママはまたわたしを紹介し、レイアウトを彼女たちに見せ始めた。「これ、あの席じゃが。上手に撮っとるわ。女性たちは口々に写真を褒めてくれる。「これ、本に載るんじゃって。すげえな」いや、そんなすごくないのですが、ここがわたしとにかくすきで。恐縮するわたしに女性たちは思い出話を始める。
「ここに移転する前からわたしら常連なんよ。もう40年くらい。ずっと通っとるうちにすっかりおばあちゃんになっちゃってな」はっはっはと大きな声で笑い合う。ずっと仲良しなんですね。すてきです。彼女たちの手の写真を撮らせてくれとお願いしたら、ハンドクリーム塗らな、と元ギャルたちはひとしきりまた、笑った。きっちり生きてきたことが窺える、どれもすてきな手だ。ともだちがいて、居場所があるってすごくいい。
またドアが開いた。ステッキをついたスーツ姿の紳士だ。「ダンケ・シェーン」ドイツ語でにやりとママに挨拶をする。はいはい、いらっしゃい。ママは動じずに笑顔で答える。どちらもしびれるかっこよさだ。少し斜めにハットをかぶり、粋な彫り物がされたステッキを持つ彼には窓際のブースが似合いそうだ。もうそろそろお暇しよう。
常連ガールズに挨拶し、コーヒー代を払う。 また来ますね。ひよっこですが、また。
ありがとうねぇ。 ママは軽快に笑った。