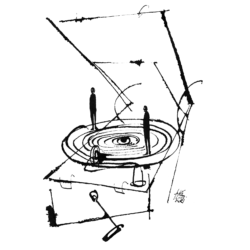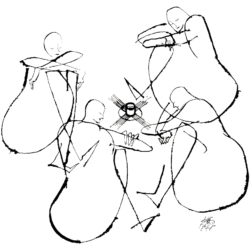珈琲の味を教えてくれた恋人
かつて、私はかなり年上の男性と多分付き合っていた。なぜ「多分」と、曖昧な表現をするのか。それは一度も「私たち付き合ってるよね?」という言質を取ったことがないからだ。良く言えば、「好き同士だからこうしてデートしている」という暗黙の了解があった。悪く言えば、「形式を求めた瞬間に、この関係は終わるだろう」という予感があった。しかし実のところ私は、「二人は恋人同士だ」という確証が狂おしいほど欲しかった。
彼と私は、よく都内某所の喫茶店に通った。閑静な住宅街の一角にある店で、店内には西洋の美しいアンティークランタンがいたるところに並んでいた。店ではいつも、彼が勧めてくる珈琲を飲んだ。
本当は珈琲の味など何ひとつ分からなかったが、彼に嫌われたくない一心で「美味しい、美味しい」と言っては涼しい顔をして飲んだ。そして毎回、文学の話をしたり映画の話をしたり、UKロックバンドの話をしたりした。正直に言えば話の半分も正確に理解していなかったと思うが、私は彼と話をしているだけで、自分の教養が深まっている気がした。時には彼に「その映画は観てない」と素直に打ち明けた。すると彼は「絶対観たほうがいいのに」と言って、膨れ面をした。その不機嫌な表情を見られることでさえ、私にとっては甘美な光景だった。
背伸びから始まった恋は、最初は楽しかった。しかし、いつからか私は、彼に好かれたいあまり偽りの自分を演じることに疲れてしまった。ある日、二人でいつもの喫茶店に向かった。そして、いつものように小説や音楽の話をしながら珈琲に口をつけた。その時、ふと「この関係はもう終わりにしたほうが良いかもしれない」という謎の予感に包まれた。いや、そんなはずはない。いま目の前に座る、ヨウジヤマモトが似合うセクシーな男のことを、私はずっと愛してきたではないか。彼は私に色々なことを教えてくれて、沢山の刺激的なことを仕込んでくれたではないか。そう自分に言い聞かせる。しかし、もう自分の気持ちに嘘は付けなかった。
結局、その日は普段通りに会話を楽しんだが、私の心はどこかうつろだった。その代わりに、これまで旨味というものを全く感じたことがなかった珈琲が、わずかに甘く感じた。気のせいだ、と自分に言い聞かせた。
数日後。いつもの店で彼と待ち合わせた。彼は細長い指先でタバコをふかしながら、海外出張の土産をくれた。それは繊細なシルクで出来た、ピンク色のスカーフだった。さっそく首に巻きつけてみると、彼は目を細めて「似合うね」と言ってくれた。あぁ、私はこの顔が好きだった。好きだった。とても。切り出すならば、今だと思った。
「こうやって会うの、もうやめよ」
彼はわずかに驚いてから、瞳の奥を揺らす。それから革製の椅子に深くもたれかかり、ゆっくりとタバコの煙を吐いた。私は不思議な高揚感に包まれていた。この選択肢しか残されていないことを、本能的に理解していたからだ。私は彼から、何もかも仕込まれすぎていた。映画も小説も、教わることは何も残っていないほど。時を同じくして、店のマスターが私たちのテーブルにやってきて珈琲を2つ置いて去った。いつも通り無愛想に、しかし、わずかに繊細さを感じる置き方で。香ばしい香りが辺りに立ち込める。微妙な空気を打ち消すように、私はそれに口をつけた。その瞬間、このあいだの哀しい予感は間違っていなかったことに気づく。私はもう、珈琲の美味しさが理解できるようになってしまっていたのだ。わずかに泣きたくなり、彼のほうを見る。それから意を決して言った。
「本当は、ずっと珈琲の美味しさが分からなかった。でも今、ようやく分かった気がする」