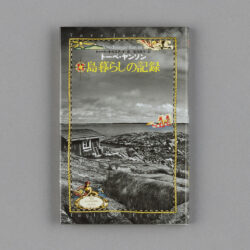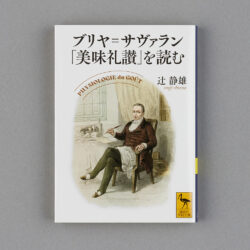カトラリーを盗んだ女
「彼はある一瞬を切り取ってわれわれに提示する。そして、その一瞬には明らかに過去と未来がある。しかし、そのふたつを見つけるのはわれわれの仕事だ」(序文より)
ここでいう「彼」とは、20世紀アメリカの画家エドワード・ホッパーのこと。「われわれ」とはローレンス・ブロックとその仲間たち。つまりホッパーの絵画からインスパイアされた短編で編まれたアンソロジー『短編画廊 絵から生まれた17の物語』に参加する作家たちであると同時に、ホッパーの絵に惹かれ、そこに物語を見出す鑑賞者のことでもある。
同アンソロジーには、スティーヴン・キングからジョイス・キャロル・オーツら豪華な面々が参加しているが、その編者であるローレンス・ブロックが題材にしたのが、1927年の作品『オートマット』(Automat)である。薄暗いカフェテリアでコーヒーカップを手にうつむく、帽子をかぶった女性。背後には薄暗いガラスに反射し、浮かぶ味気ない店内照明。タイトルが示さなければ、ひと目でここが「オートマット」だと分かる人はそう多くはないだろう。
「オートマット」とは20世紀初頭のニューヨークで流行した自動販売機式のカフェテリアのこと。硬貨1枚でスープからパン、コーヒーまでが自動販売機で温められ、提供される。昨今のコロナ禍において非接触型のサービスに着目、再オープンされたことも話題となった。流行りはじめは話題のスポットとしてもてはやされるようなこともあっただろうが、どう考えても美食やサービスの質を求める客が集まる場所ではなかったはずだ。そんな店で、釣鐘型のクローシェ帽に、襟と袖に毛皮があしらわれたコートという、整った身なりの女性がうつむき加減でひとりコーヒーを飲む姿はずいぶん場違いではないだろうか。そもそも状況説明のために「オートマット」を描くのであれば、特徴的な食品販売機にフォーカスするだろう。あきらかに特殊な状況で、かつ何らかの事情があるに関わらず、それを明示するような決定的瞬間を描かないことこそが、ホッパーの絵を観たものにストーリーを渇望させるのだ。
ローレンス・ブロックの短編では、『オートマット』の彼女は、夫を失い、日々の生活費にも逼迫する零落した身として描かれる。一見身だしなみはノーブルだが、よく見るとコートも帽子も随分と着古されたものだ。妄想の中で亡き夫と対話しながら、彼女はある賭けにでる。持参したカトラリーを店の人間の目につくようにバッグにしまい込む。そそくさと店を出ようとする彼女に店主は声をかけ、盗みの疑いをかけるが……。
拳銃と女さえいれば映画はできるとは、ゴダールの発言だったか。ホッパーの絵になぞらえていうならば、場末とそこにそぐわない女とコーヒーがあればサスペンスが生まれる。
現代に置き換えてみれば、コンビニエンス・ストアのイートインスペースで100円のコーヒーを飲む上品な女性の姿は果たして絵画や映画になり得るだろうか。少なくともホテルのラウンジで毒入りのコーヒーを口にしてカップを落とすような陳腐な演出よりも、個人的には好みの作品になりそうだ。