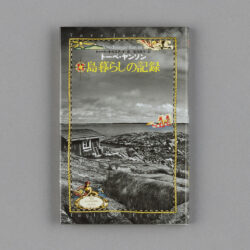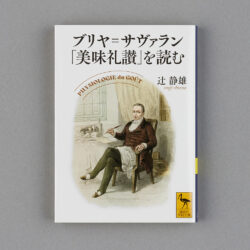失われた「ちょうどいいカフェ」を求めて
「それは、あたたかく、清潔で、親しみのある気持ちの良いカフェだった。私はコート掛けに私の古いレインコートをかけて乾かし、ベンチの上の方の帽子掛けに、自分のくたびれて色のさめたフェルト帽をかけ、牛乳入りコーヒーを注文した。ウェイターがそれをもってくると、私はコートのポケットからノートブックを出し、鉛筆をとり出して、書きはじめた」(『移動祝祭日』アーネスト ヘミングウェイ著、福田陸太郎訳)
パリ6区のカフェ、「クロズリ・デ・リラ」には作家フィリップ・ソレルス専用の席があり、彼が訪れようが訪れまいがそこに他人が腰掛けることは決して許されなかったという。これが政治家や資本家のための席であればただの権威主義である。しかし、戦後においてなお、作家専用の席を維持し続けるというあたりに、このカフェの、文化の守護神たらんとする矜持が見て取れる。
一九二〇年代の前半、小説家としての修業時代をパリで過ごしたヘミングウェイもこのカフェの愛用者のひとりだった。カフェ・オ・レではじめ、興が乗ってくるとワインやラム酒に切り替え、ひと仕事を終え空腹を覚えると、牡蠣を一ダースほど食する。かつてのパリのカフェとは、もの書きにとっての仕事場であり、食堂であると同時に社交場でもあった。
パリ時代を回想した遺作『移動祝祭日』には、「クロズリ・デ・リラ」で物書きの知人から絡まれる一場面が描かれている。仕事の邪魔をするように話しかけてくる男に対して、席を外すこともできたはずだが、頑なに無視を続け、話しかけられながらも、ペンを離さずに書き続ける理由は、そこが「ホーム」であったからだ。自分だけの定位置があり、遠慮なく仕事が続けられ、メニューを見ずとも注文ができる。そんな居心地は、通い詰めることでようやく手にすることができるのだ。それを酔客ひとりのために易々と手放すわけにはいかない。彼はカフェを訪れない日のことを「クロズリに一日の休暇を与える」とまで表現した。
それから百年後の日本では、随分と仕事ができるカフェや喫茶店がすっかり少なくなってしまった。自ら「サードプレイス」を謳う外資系チェーンは、ノート型パソコンと資料である書籍をあわせて置くにはテーブルが狭すぎるし、個人経営の喫茶店で長時間キーボードを打つのも店の人に申し訳なくって、気が引けてしまう。注文ならいくらでもするかわりに、ひと目が気にならず、かといって静か過ぎて振る舞いに神経質にならないようなカフェは一体どこにあるのだろう。かつては、外資系でも個人店でもない、ローカルチェーン店がどのエリアにもあって、そこが仕事場の役割を担ってくれていた。
現代の京都にヘミングウェイがいたならば、彼は一体どこで仕事をしたのだろう。そんなことを考えながらこの原稿を、「ロイヤルホスト 北山店」で白ワインを飲みながら書いている。