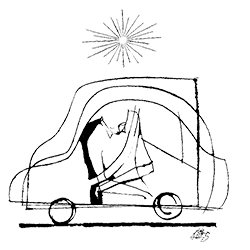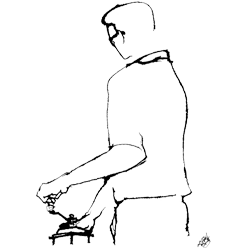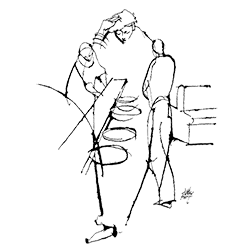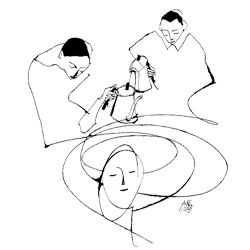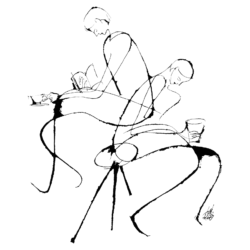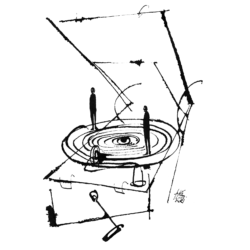マスター
まだ高校生の頃、新聞配達のアルバイトでためた金で、街一番のデパートへ行き、奮発してサイフォン式の器具を買った。昔ながらの喫茶店のカウンターに並ぶ、上下にフラスコが分かれて瓢箪のような形をした、あれである。潜水艦の鉄のハッチのような重厚な蓋のついた豆挽き器も買った。アルコールランプに火を点じると、下のフラスコの水が沸き、蒸気圧でガラスの管を伝って粉のある上のフラスコに湯が昇り、ゴボゴボと混じり合う。思わず、うおっと声をあげた。珈琲とは、かくのごとく淹れるものかと、西洋文明に触れたちょんまげ頭のような気持ちになった。九州のはじっこの工場街で一緒に暮らしていた親たちは、インスタントコーヒーに砂糖とクリープを入れて飲むのが当たり前だったから、息子がいきなり本格的な器具を買ってきたことにやや当惑していた。コーヒー茶碗につぎ分けて、得意になって家族たちにふるまっていたが、そのうちにめんどうになってやめてしまった。その頃の僕は、どこか大人の香りがする喫茶店のマスターになることに憧れていた。
その後上京して美術大学の学生寮に暮しはじめたが、豆挽き器だけは持って来て、布のフィルターで珈琲を淹れるようになった。しかし、夏場はアイスコーヒーを飲むために、廊下にあった足踏みのペダル式の水飲み器の冷水でインスタントコーヒーを溶いて飲んだ。なにしろめんどうくさがりやで、いまも、風景画を描くときに瓦の数を数えたり、木の枝や葉の複雑な形を追うのが苦手で、大ざっぱに適当に描く。しかし、絵はこれでよいが、やはりコーヒーは、丁寧に淹れないとうまくない。
豆挽き器のハンドルをまわし、ガリガリ豆をつぶして珈琲を淹れる時間は、めんどうくさがりの僕にとっては、寺で座禅を組んで心を浄めているような気分にさせた。しかし、それもあるときとうとう電動ミルにかえてしまい、一連の動作が消えてなくなったことで、どこか挽いた豆の魂がぬけてしまったふうであった。僕はマスターには向いていないように思われた。
しかし最近は、どういうわけかまったくインスタントを飲まなくなった。というか、飲めなくなった。大好きだったインスタントラーメンなども体がまったく受けつけないのである。もう一生分、飲んだり食べたりして飽和量に達してしまったか……。あるいは、年齢のせいか。
好きな豆を買ってきて、ペーパードリップで濃いめに淹れたのを瓶に移し、冷蔵庫で冷やしておいて、氷を浮かべている。挽いた粉に少し冷ました湯をたらす。しばらく待ってから湯を細く注ぎはじめると、挽いた豆の粉がもっこりと膨らんで、豆が香りはじめる。ケトルから細くゆっくりと湯を注ぎ足す間、手指のストレッチなんかやる。うまいアイスコーヒーを飲みたいとやっているうちに、いつのまにかこういう手間が愉しくなっていた。コーヒーの粉が、もっこりと膨らむ様子をただ見たいがために、淹れたいという欲求さえ、感じる。ちょっと気分を出そうと、コーヒーを落とすために、わざわざジャズをかけたりもする。サイフォンから四十年以上たち、いまごろになって、ようやく昔憧れたマスターに近づけたような気がしている。