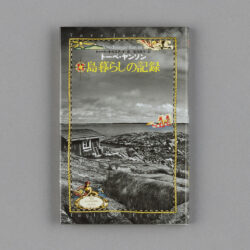触れて、見て、聴こえる味。
「全身の力を抜き、右手を右のこめかみに軽く当てて目を閉じます。レストランのざわめきも音楽も、同席している友人達の会話もみな消えて、私は闇の中にひとり坐って、無念無想でそのものを味わっているというつもりになるのです」(「幻のソース」)
向田邦子はこのようにしてよそで食べた味を記憶して帰り、調理法を模索し、再現してみせたという。どこか魔術めいたこの儀式に象徴されるように、彼女のエッセイに登場する食にまつわる描写は、いつも記憶や風景のような、味覚以外の感覚と強く結びついている。プルーストのマドレーヌが、向田邦子にとっての伊勢海老であり、さつま揚げなのだ。
例えば水羊羹を語るとき、彼女は味のことにはほとんど触れていない。良い水羊羹の条件としてまずは「鋭い切り口と、手の切れそうなとがった角」を挙げ、蛍光灯の下ではなく「すだれ越しの自然光か、せめて昔風の、すこし黄色っぽい電灯の下」で味わうことを推奨し、もっとも相性の良いBGMとしてミリー・ヴァーノンというジャズ・ヴォーカリストの「スプリング・イズ・ヒア」という具体的なアルバムを迷うことなく選んでいる。口にしたものを、触覚、視覚、聴覚に置き換える彼女はまるで共感覚者のようだ。
彼女がコーヒーにまつわる思い出を綴った「一杯のコーヒーから」というエッセイがある。タイトルと同名の、服部良一のペンによる昭和13年のヒット曲を、母の鼻歌で聞きながら育った彼女は、「子どもが飲むと夜中に騒ぐ」という理由でコーヒーを禁じられたがゆえにその味わいに憧れを持ったまま大人になる。出版社に勤め映画雑誌の編集を続けるある日、彼女の文才を見込んだ広告マンから、テレビ脚本執筆のアルバイトを持ちかけられる。その後の歩みを知る読者としては、ここが彼女の人生の分岐点であり、輝かしいキャリアのスタートだということがわかるはずだ。その時にいた喫茶店で飲んだアメリカン・コーヒーの味わいには触れず、閑散とした店内の様子と、「いやに分厚くて重たいプラスチックのコーヒーカップ」だけが記憶に刷り込まれているという。その後彼女は周知の通り脚本家となり、コーヒーを飲みながら遅くまで仕事をする夜型人間として生きていくことになる。
コーヒーについての薀蓄や好みを一切語ることなく、人生の分岐点に一杯のコーヒーがあった、という事実だけが綴られるこのエッセイのビターな味わいはなんだろう。鼻歌を聞かせながら子どもを育て、夜ふかしのしないもうひとつの人生の可能性。そこへと至る道から足を踏み外させた一杯のコーヒーが、喪失感や覚悟のような感覚とリンクし、読むものに不思議な余韻を残す。人生を狂わせたコーヒーの味を彼女はこのようにして綴ったのだ。